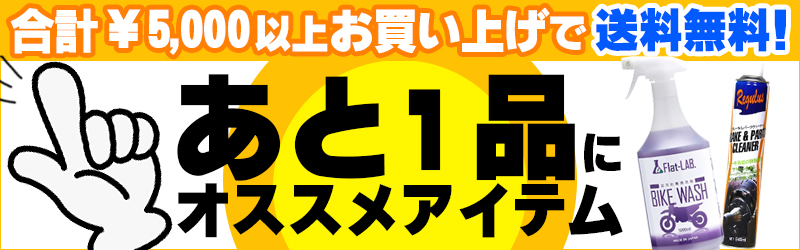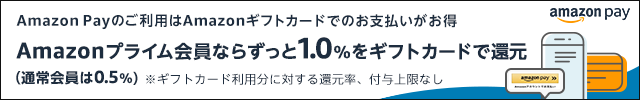2025年3月更新ダートバイクプラスTIPS・今回はおすすめのゴーグルについてお話したいと思います。
シールドじゃなくて?そもそもオフロードでゴーグルを使う理由とは
オフロードバイクのヘルメットには、シールドが付いたものと、シールドが無くゴーグルと組み合わせて使用するものがあります。
一般的にオフロードヘルメットと言うのはゴーグルと組み合わせて使用するのが通常のタイプで、 シールド付きのモデルがツーリング向けになっています。
どうしてオフロードではゴーグル仕様になっているのか?
一見するとシールド付きの方が便利そうに見えますが、 オフロードにおいてゴーグルを着用する理由は大きく3つあります。
シールドだと息が苦しいので、呼吸がしやすいように開口部を作りたい
ゴーグル仕様なら口元が開いているので、運動量が多いモトクロス・エンデューロでも呼吸は快適です。
泥や曇り対策のためにゴーグルとしてヘルメットから独立させたい
オフロードゴーグルには悪天候などでレンズに付着する泥対策として、ティアオフやロールオフというオプションがあります。 こうしたオプションを装備するためにはヘルメットから独立したゴーグルが何かと便利なんですね。
オプション・リペアパーツの豊富さと入手性
シールドに比べると安価にレンズ交換が可能な点。
シールドは大抵4,000円以上するものですが、ゴーグルレンズは安価なものなら1,500円程度で手に入ります。
どうしても石や砂が当たって傷が付きやすいものなので、こうしたリペアが容易なのもオフロードゴーグルならではのメリットです。
ゴーグルを選ぶ際のポイント
ここからゴーグルの選び方についてお話しましょう。
ゴーグルのメーカーも色々ありまして、メーカーごとに特徴や価格帯もさまざまです。
なので、各メーカーのポイントを押さえたうえで、自分にマッチするものを選びましょう。
メガネに対応してるかどうか
まずこれが大前提・メガネを着用するか否かでゴーグル選びが変わります。
普段メガネを着用していても、バイクに乗るときはコンタクトという方もいらっしゃるので
先に自分の方針を決めておくと良いですね。
メガネに対応しているオフロードゴーグルは、メガネ越しにゴーグルを着用出来るよう、
横幅が一般的なゴーグルに比べて広く、奥行きもやや深めでゆとりのあるフレーム形状になっています。
また、一部のメーカーではメガネのツルが納めやすいように
スポンジに切り欠きを付けているものも。 このように、メガネ対応ゴーグルはメガネに合わせた特徴を持っていますが、 幅広タイプのツルや大きなレンズのメガネ(勉三さんメガネ)は収まらないこともあります。 そうでなくともブランド物のメガネに破損や傷が付いてしまうと大変なので、
オフロードバイク用に小振りなメガネを用意してもいいかもしれません。今どきは5,000円程度で安価にメガネが作れますしね。
実店舗で購入される際には実際に試着して、装着感を確認して決めましょう。 こうした点がメガネ対応ゴーグルの特徴ですが、裸眼やコンタクト着用でバイクに乗るという方は
メガネ対応ゴーグルを選ぶ必要はありません。通常の裸眼用モデルを選べばOK。
後述しますが裸眼用モデルの方が本体・オプション共に種類は豊富です。
レンズ・オプションパーツの豊富さ
オプションレンズ
レンズ交換がしやすいのがゴーグルの魅力の一つですが、
それもレンズが供給されていればこそです。
メーカー・モデルによってはクリア・スモークしか出ていないものもありますが、
それよりはファッション性もあるミラーレンズなど色々選べた方が楽しめるでしょう。
スイス発の老舗ゴーグルブランド・SCOTTのゴーグルレンズを例に挙げると、
クリアやスモークレンズはもちろんのこと、
各色ミラーレンズに曇り対策に効果を発揮するダブルレンズや、
紫外線に反応してレンズの色が変化するライトセンシティブレンズなど、とても豊富なラインナップがあります。
中でもダブルレンズは寒冷地の二重サッシと同じ理屈で、
2枚のレンズの間に空気の層を設けることでレンズの結露=曇りを強力に防ぐ効果があります。
雨の日や激しいエンデューロなどでは非常に有効です。
オンロードバイクでもピンロックシールドという二重レンズが一般的になりましたしね。
ティアオフ・ロールオフ
オフロード走行ではあちこちから泥や砂が飛んでくるので、
跳ねた泥などで視界を遮られることもしばしば。
そうした場合に視界を回復してくれるのがティアオフやロールオフというゴーグルオプションです。
ティアオフというのはゴーグルレンズ表面に固定する透明のフィルムです。
雨天のレースではこれを数枚重ねてゴーグルに装着し、泥が付着する度にこのフィルムを剥がしていきます。
これによって視界を回復させるのがティアオフの役目。
ティアオフはモトクロスライダーにとって唯一暇な場所・空中で剥がすのが基本。こんな風に剥がせるとカッコいいですね。 ティアオフは軽量かつ、ゴーグルレンズ全面を覆っているのでとても使いやすい反面、一度のレースで装着出来る枚数は5枚程度という制限があります。 理由は透明のフィルムであっても、重ねることで透明度が下がってしまうから。その対策として、7枚程度のフィルムを熱処理によって半分程度の厚みに加工することで、
透明度を下げずに重ねた「ラミネートティアオフ」というものもあります。これなら最大21枚程度のティアオフを装着することが可能です。
ロールオフはティアオフでは対応しきれないほど泥が繰り返し飛んでくる状況や、
環境保全のためティアオフの使用が禁止されているレースにおいて使用される装備です。
ゴーグルのレンズ左右にフィルムを巻き取るためのユニットを装着し、 ゴーグル左にあるゼンマイのついた紐をギーコギーコと引っ張ることで、
新しいフィルムが右から左へとレンズ表面に移動します。これにより常にクリアな視界がキープ出来るという仕掛け。 レンズの全面を覆っているわけではないため、回復出来る視界は全てではありませんが、ティアオフに比べ30回以上の視界回復が可能です。 このように、それぞれに特徴があるので、
天候や路面の状況・レースのレギュレーションに合わせてティアオフとロールオフを使いわけて使用します。 ティアオフもロールオフも基本的にレースで使用するアイテムなので、 林道ツーリング主体の方であればこうしたオプションはまず必要ありませんが、 逆に言うとこの辺りが充実していないとレースでは困ってしまいます。ゴーグルの選び際には重要なポイントと言えますね。
メーカー・ブランド重視で選びましょう
前述の話と繋がる話ですが、有名メーカー・ブランドであればオプションレンズ・パーツ共に
ラインナップや供給はしっかりしているのでゴーグルの維持管理もしやすいでしょう。 品質ももちろん保証されているので、基本的に悪いゴーグルというのはありません。 視界の良さは勿論のこと、UVカットやフィット感を高める細かな工夫など、
各メーカー良く考えられた製品作りをしています。 ゴーグルは目を保護する大切な装具なので、安いからと言って正体不明のコピー商品を使ってしまうと
思わぬ怪我をしてしまう可能性があります。傾向としてフリマアプリや大手通販サイトでコピー商品は多く出回っているので、
販売元やメーカーをよく確認して購入した方が安心ですね。
オフロードバイクで使うおすすめのゴーグル6選
オフロードバイクのゴーグルの必要性や選び方を説明したところで、
ここからはおすすめしたいゴーグルの紹介に移りましょう。
以下、順不同となります。
SCOTT(スコット)
SCOTTは1958年にアメリカ・アイダホ州でスキーポールの会社として設立。1970年にはモトクロス市場に参入し世界初のモトクロス専用ゴーグルをはじめ、MXブーツやグリップ等数々の画期的な商品を世に送り出しました。その後、スイスに本社を構える総合スポーツメーカーに発展し、モーターサイクル用品から自転車の車体からスキー用品まで広く手掛けています。SCOTT・FURYゴーグル
SCOTTのラインナップの中でも、ミドルライン(中間グレード)に位置しているのがFURYゴーグル。
FURYと言うのはフューリーと読みます。
SCOTTのラインナップ内では更に上級モデルのPROSPECTや、エントリーモデルのPRIMALがありますが、
コストパフォーマンスと性能のバランスが最も良いと言えるのがこのFURY。
レンズはPROSPECTと共通の大型タイプで、視界を広く確保。レンズカラーも豊富に揃っています。
また、オプションのロールオフシステムも50mmの幅広タイプになっていて、悪天候のレースでも通常の35mm幅に比べ広い視界を回復出来ます。
顔にフレームは日本人にも比較的フィットしやすい湾曲の少ない形状で、三層構造のスポンジとの組み合わせでフィット感に優れます。
独特のレンズ着脱機構により、一般的なゴーグルに比べレンズ交換が比較的容易になっています。
これは出先でのレンズ交換もストレスフリーで行えるので便利ですね。
このように機能とオプションが充実していながら、価格がノーマルレンズ仕様で税込み定価9,900円。
ミラーレンズ仕様で12,100円と比較的リーズナブルなのが嬉しいポイントです。
[card_p : product_id=31287][card_p : product_id=36074]FOX RACING(フォックスレーシング)
FOX RACINGは1974年に創業した、モトクロスを発祥とするスポーツメーカーです。
モトクロスとMTBギア全般を製造しており、特にモトクロスにおいては常にNo.1ブランドとしての地位に君臨しています。
ヘルメットからブーツまで全ての用品をラインナップしているため、勿論ゴーグルも押さえています。
FOX・VUEゴーグル
FOXーグルの中でもハイエンドモデルに位置するVUEゴーグルは、他メーカーとは異なる独自のレンズロックシステムによって、
飛び石などのレンズを突き破りかねない威力の高い衝撃にも強い耐性を持っています。
具体的には、通常のゴーグルがレンズの縁を挟むように固定しているのに対し、VUEゴーグルではレンズを本体に被せるように固定しています。
そのため、対貫通性能が非常に高く、450ccなどのハイパワーマシンの巻き上げる強烈な飛び石にも耐える強さを持っています。
更に、そのレンズは通常のゴーグルより厚みがあり、カーブが付いた状態で成型されているため
丈夫で歪みの少ない視界を確保しています。そのためより実戦向きと言えるでしょう。[card_p : product_id=35854]↓↓サイクル用↓↓[card_p : product_id=36102]
PROGRIP(プログリップ)
ヨーロッパを代表する、その名の通りハンドルグリップで定番のメーカーですが、
ゴーグルやモトクロスウェアなどの用品も充実しています。
その中でもオフロードゴーグルはコストパフォーマンスに優れた無難な選択として人気があります。
PROGRIP・3201レースラインゴーグル
PROGRIPのエントリーモデルであるレースラインゴーグルですが、
入門用と侮るなかれ、価格と品質が良い意味で釣り合っていません。
税込み定価が4,180円でありながら、作りにコストダウンを感じる妥協点が見当たらないのです。
中でも顔に当たるスポンジフォームは三層構造。
顔の汗が目に入らないよう、極厚のスポンジでしっかりと吸収してくれます。
また、フレームとスポンジにはメガネのツルを避ける加工がされているので、メガネにも対応可能です。
因みに、商品名の3201というのはフレームの型番を意味しており、
3201対応とあればスペアレンズなどの各種オプションが対応致します。
ミラーレンズからティアオフ・ロールオフまで一通り揃っているのでレースユースにも安心ですね。
[card_p : product_id=30977]
OAKLEY(オークリー)
アメリカのカルフォルニア発のアイウェアブランドであるOAKLEYは
サングラスやスキー・ゴルフ用品でもおなじみのブランドですね。
昔はオークレーと呼んでいましたが、近年はオークリーと呼ぶのが正しいと言われています。
呼び方で世代がわかるのが面白いところですね。
OAKLEYの始まりはモトクロス用グリップだったのは意外と知られていないことですが、
それ故か、オフロードゴーグルにおいても定番のトップブランドの一角となっています。
現在はメーカーの供給が不安定で、オプションパーツの入手性にやや難がありますが、
品質はアイウェアブランドということで確かです。
OAKLEY・O-FRAME2.0 PRO MX
OAKLEYで30年以上に渡り販売されてきたO-FRAMEの後継・発展モデルがこのO-FRAME2.0 PROです。
特徴なのはメガネ対応でありつつ、裸眼用でもある兼用タイプであるということ。
フレームのサイド部分がカットされた形状のため、メガネのツルを圧迫することなく顔にフィットします。
鼻・口周りに泥が付着することを防ぐノーズガードが標準装備。任意で取り外しも可能。
メガネ対応ゴーグルは各メーカーにラインナップされているものですが、
カラーバリエーションの豊富さではOAKLEYは他の追従を許しません。
人気モトクロスブランド・TroyleeDesignsとのコラボモデルも定期的に発売され、人気を博しています。 [card_p : product_id=35964][card_p : product_id=35970]
100%
かつてデカールブランドとして存在した100%。
一度はその存在を消してしまいましたが、2012年にゴーグルブランドとして再始動。
現在はオフロードゴーグルにおいてトップクラスの人気を得ており、歴史は浅いながらもすっかり定着しました。
RACECRAFT2(レースクラフト2
100%ゴーグルの中でもハイエンドモデルに位置するのがRACECRAFT2。
現在は更にフラッグシップとして上位モデルのARMEGA(アルメガ)が登場していますが、RACECRAFT2も業界トップクラスのクオリティを確保しています。
特徴的な形状とは裏腹に、細部まで堅実な作り。
フィット感に優れる三層構造のスポンジに、アウトリガー付きフレームで顔への着圧を適切に保ちます。
アウトリガーというのはゴーグル本体から伸びた、ストラップが接続されいてるアームのこと。
比較的高グレードのゴーグルに採用されている構造で、
ゴーグルを掛ける際、ヘルメットに干渉せず真っすぐ顔へとフィットさせられる効果があります。
オプションレンズ・ロールオフなども充実しています。
特にカラーリングの豊富さとデザイン性の高さが人気のポイントです。
[card_p : product_id=36582][card_p : product_id=36583]
SWANS(スワンズ)
海外ブランドの多いオフロードゴーグルの中では珍しい国内メーカーで、山本光学という会社のブランドです。
そのため、比較的彫りの浅いとされる日本人の顔にフィットしやすいフレーム形状が特徴。
海外ブランドでは頬骨が圧迫される・鼻が浮くという方でもSWANSなら違和感なくフィットするでしょう。SWANS MX-TALON
SWANSゴーグルの中でハイエンドモデルに位置するMX-TALON。
特徴的なのは、顔に当たるスポンジ部分とストラップの交換が可能な点。
通常、この2点は消耗品ではあるものの交換できるゴーグルはほぼ存在せず、劣化したら本体ごと買い替えというのが常識でした。
それが低コストで交換可能ということで、リペア次第で長く使えるゴーグルになっています。
もちろんジャパンフィット・アウトリガー装備なので着け心地も抜群です。
[card_p : product_id=33543]
まとめ
以上、ゴーグルの機能解説と選び方のお話でした。
近年ゴーグルは価格の上限が無くなってきており、2~3万円するものも多々ありますが、
しっかりとした有名ブランドのものであれば、5,000円以下のものでも全く問題ありません。
価格よりも重要なのは
用途に適しているかどうか(レース・ツーリング・裸眼・メガネなど)
オプションパーツが充実しているか
カッコいいデザインかどうか
自分にフィットしているか
こうした点を押さえて選べば、自分にあった最適なゴーグルが見つかると思います。オフロードバイク用品買うなら!ダートバイクプラスを是非どうぞ!
もっと読む