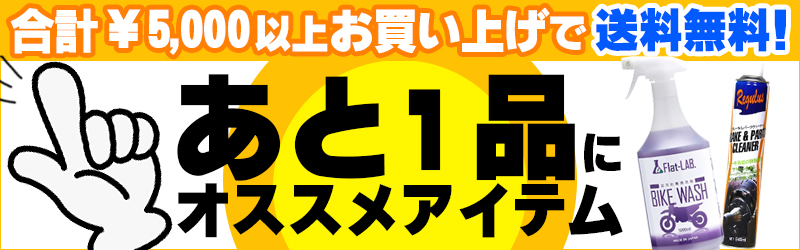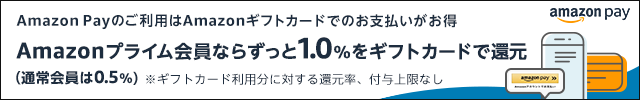スマホの充電を極める!バイク用USB充電器の選びかたを徹底解説
スマホや電子機器の充電に悩める人類の皆様こんにちは。充電神の寺尾です。今日はスマホの充電について解説していきましょう。充電器を語る前にスマホの解説スマホの充電でまず意識したいのは、お手持ちのスマホがiphoneか、アンドロイドか?という点。iphoneはご存じLightning端子というものを採用しています。多分今後も2年くらいはLightningは続くだろうと言われていますが、とにかくiphoneと言えばLightningです。一方のアンドロイドスマホは、3年くらい前のモデルからほとんどのモデルがUSB-TypeCという規格を使用しています。俗にUSB-C端子って呼びます。使用する充電器がType-A(普通のUSB端子)の差し込み口であれば、充電ケーブルをそれぞれLightning、またはUSB-Cのモノを用意すればOKです。お使いのスマホに合わせてご用意下さい。しかし、デイトナの充電器では差し込み口を廃した直接充電出来るタイプも出ているので、こちらを選択する際には、購入前に端子の確認をしましょう。充電スピードは早い方が良い次に確認すべきは充電出力です。出力が高ければ充電スピードは上がるので、出先で写真を沢山撮ったりしてバッテリー残量が少なくなっても素早い回復が可能です。各充電器には、必ず充電出力が記載されているので、ここをチェックして選びましょう。アンペアなのかワットなのか。表記の罠ただ、ここで引っかかる要素が。充電器を選んでいると、おかしな点に気づくはずです。出力の表記がA(アンペア)表記とW(ワット)表記が混在しているのです。これではイマイチ比較が難しいですね・・・。でも、計算すれば簡単です。例えばこちらの充電器の場合、5Vの2.1Aと記載されていますね。これを掛ければW表記として比較できます。つまり5×2.1で10.5Wということ。因みに10.5Wと言うのはバイク用充電器としては標準的な出力。つまり普通の充電スピードです。因みに、少し前までiphone付属していた充電コンセントは5Wです。これは今時の充電器としてはかなり遅めだったりします。20Wなどの急速充電器に変えるとビックリするほど充電が早くなりますよ。最近のスマホは急速充電対応最近のトレンドとしては、このように18Wという高出力の充電が可能なものもあります。iphoneであればiphone8以降のモデルが。androidではType-C端子でPD対応と言うモデルであればこの急速充電に対応しているので、スピーディーなバッテリー回復が可能です。(Power deliveryと言うのはUSB-Cの中でも急速給電に対応した規格)せっかく充電器を装着するなら充電速度は早い方が良いですよね。旅先でスマホのバッテリー残量が少ないときほど心細いことはありません・・・具体的な充電器の選びかたここからは、貴方のバイクと使い方に合った充電器を具体的にどう選ぶか?というお話に入りましょう。これまで解説したポイントは、お使いのスマホがiphoneかandloidかの確認。そして充電出力=充電スピードの二つ。では、次に考えるべきはなにか?それは、取り付けスペースや収まりの良さ。近年のバイクのハンドル周りはスマホのホルダーやカメラマウントなどでハンドルの空きスペースを圧迫しがち。充電器も、取り付けるスペースがあるか?邪魔にならないか?という点を考慮する必要があります。ド定番の充電器[card_p : product_id=29141][card_p : product_id=24585]例えばデイトナの一番スタンダードな充電器であるコチラ。インシュロックで縛るだけの簡単固定なので、スペースさえあればハンドルのどこにでも取り付け出来る点が便利です。2Pタイプも用意されているので、スマホとカメラの同時充電なども可能。ただ、固定方法の都合上、取って付けたような見た目にはなりやすいですね。省スペース化に優しい[card_p : product_id=27567][card_p : product_id=30677][card_p : product_id=27566]次に紹介するのは見た目がスマートな横幅を押さえたスリム仕様。左の集中スイッチに並ぶ形で配置出来るので、スペースを最小限に抑えることが出来ます。USB-Cの差込口でコンパクトに[card_p : product_id=30674]続いて紹介するのは差し込み口がUSB-Cを採用した充電器。通常のType-A端子に比べコンパクトに出来るので、取って付けた感が抑えられますし裏・表の区別もUSB-Cには無いので挿し間違いもありません。充電と同時に電圧も管理したい[card_p : product_id=30624][card_p : product_id=30623]こちらは充電器と電圧計を一体化させたタイプ。充電器とグリップヒーターなど、電力消費の大きな機器を複数装備するために電圧の管理もしたいという方も多いかと思います。充電器として使用しない場合であってもバッテリー管理が出来るので単独で電圧計を付けるくらいであれば、こちらを選択するのもアリでしょう。煩わしいケーブルを廃したワイヤレス充電[card_p : product_id=30680]対応するスマホは限られますが、最も便利かもしれないのがコチラ。Qi(チー)と呼ばれるワイヤレス充電タイプです。スマホホルダーに固定して使用するため、充電器とスマホホルダーの設置スペースを一体化出来ますし、充電ケーブルの抜き差しも、iphoneとアンドロイドの区別も必要ありません。ケーブルの抜き差しをしなくて良いというのはコンビニ休憩などで大変便利です。iphoneシリーズではiphone8以降のモデルが、アンドロイドでは一部のモデルがワイヤレス充電に対応しているのでこれを活用しない手はありません。充電スピードも15Wと、中々のスピードです。充電器とケーブルを一体化[card_p : product_id=30675][card_p : product_id=30676]省スペース化のアイディアは他にもあり、こちらは充電器とUSBケーブルを一体化させてしまおうという発想で作られた充電器です。バイク用として使いやすいL型の端子で、かつケーブル長もバイク用として最適化されているので一般的なケーブルよりも断然使いやすく出来ています。ただし、ケーブルの切り替えが出来ないため、iphoneとアンドロイドのどちらか一方のみに対応します。購入時に間違えないよう注意して下さいね。結局どれを選べばいいんだいこのように、充電器にはデイトナの中だけでも沢山の種類がラインナップされています。それぞれに出力の違いやコンパクト化へのアプローチが異なるため、好みにあったものを見つけてください。筆者のオススメはワイヤレス充電タイプです。ケーブルの抜き差しが不要なのはとても便利ですよ。デイトナの用意している充電器の特性一覧表を掲載しますので、コチラを参考にして頂くと選びやすいかと思います。(クリックで拡大します)バイク用USB充電器のことならダートバイクプラスへ!!ダートバイクプラスではこの記事でご紹介したUSB充電器を数多く取り揃えております。ガジェットに強いスタッフが常駐しておりますので、わからないことがあればお気軽にお問合せ下さいね。
もっと読む