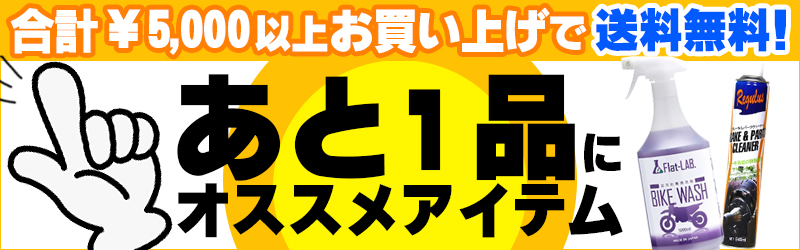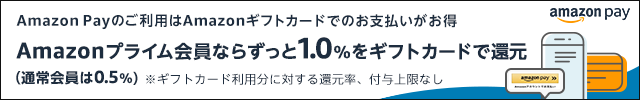オフロードバイク タイヤの空気圧のお話
オフロードバイク・タイヤの空気圧のお話今回はオフロードバイクのタイヤ空気圧はどう設定すればいいのか?ビードストッパーってなに?ハードチューブ?ムース?よくわかんない~という疑問を全て解決しようと思います。大変タメになる記事です。空気圧とは?空気圧とは、タイヤの中の空気の圧力のことを差します。オフロードバイクであればチューブホイールが一般的なので、チューブの中に入れる空気の量=空気圧となります。セローやトライアルバイクのリアホイールはチューブレスホイールなので、こちらはそのままタイヤ内の空気の量=空気圧ですね。で、この空気圧というのは高ければ高いほど燃費は良くなり、軽くバイクを動かせるようになります。自転車もそうですよね。タイヤの空気が抜けた自転車を漕ぐのは凄くしんどいはずです。ロードバイク(自転車)とか10kgくらい入れたりしますよね。しかし、空気圧は高ければ良いと言うものではありません。空気圧を高めすぎると、タイヤがカチカチになってしまいグリップ力が悪くなります。(滑りやすくなってしまいます)動力を路面に伝えることがタイヤの役目ですから、高すぎず、低すぎず、適度に路面を捉えられる空気圧の管理が必要になるということです。適切な空気圧管理のためにはしっかりとした品質のエアゲージが必須です。DRCのG102エアゲージはオフロードにおける低圧専用ゲージを採用しているため、1.0kg以下の低圧でも精度の高い管理が可能になっています。[card_p : product_id=25338] 具体的な空気圧設定は?以上が空気圧の基本的な考え方ですが、オンロードで走る場合はメーカーの指定空気圧で基本的に問題はありません。定期的に空気圧が下がっていないか確認して、必要に応じて補充してあげれば良いのですが、オフロードではよりシビアな空気圧管理が求められます。オフロードというのは文字通り未舗装路なので、固く締まった路面からぬかるんだ路面、岩や木の根と路面の固さからデコボコ具合まで多種多様です。こうした路面をタイヤが捉えて動力を伝えるためには、タイヤを積極的に変形させる(たわませる)必要があります。どのくらいの空気圧かと言うと、固く締まった路面で0.8-1.2kg程度。ぬかるんだ路面や岩・木の根の多い路面では0.2kg-0.5kg程度です。この数字はオンロードでは考えられないような低圧です。1.0kgを下回ると、タイヤは手で押すと容易に変形させられるような柔らかさになります。その柔らかさによって、路面を掴み・グリップしてエンジンの力を推進力として進むわけですね。では、空気圧を低くすればするほどグリップが増していいんじゃないのか?という疑問が出てきます。実際低圧にすればドンドングリップは増すのは事実です。しかし、タイヤが柔らかくなればなるほど踏ん張りが効かなくなってしまうと言う副作用が出てきます。モトクロス・ハイスピード走行における空気圧設定スピードを出して走る場合、つまりモトクロス的な走り方をする場合にはハイスピードに耐える踏ん張りが必要となります。人間もダッシュするときは足に力を入れるのと同じで、足がフニャフニャではダッシュ出来ないでしょ。 そんな訳で、空気圧は低圧であれば良いと言うわけでなく路面状況や走り方によって適時調節することが大切なんですね。上記に挙げたように、固く締まった路面をハイスピードで走るような場合には比較的高めの0.8-1.2kg程度に設定します。パンクのリスクも低く、タイヤの捩れも少ないので安心して攻めれる空気圧設定ですね。コンディションの良いモトクロスコースや、林道ツーリングで走る場合にはこのくらいの設定が無難と言えます。エンデューロ・難所における空気圧設定では、ぬかるんだ路面や岩・木の根の多い路面ではどうでしょう。このような荒れた路面ではハイスピードで攻めることは難しい・・・つまりスピードは出せないでしょう。そして路面をしっかり掴んで走るためタイヤも大きく変形させて走る必要があります。そこで、空気圧を0.2kg-0.5kg程度まで落とすわけです。ここまで落とすと、銘柄にもよりますが手でグニグニとタイヤが潰せる程に柔らかくなります。つまり、路面を掴む力は非常に強い。岩で滑らず、木の根に弾かれず、しっかりとバイクを前に進めてくれるようになります。空気圧を低くすることによるトラブルと対処法空気圧の設定についてはこのようなお話となります。では、空気圧の調整だけしっかりすればOKか?と言うとまだ終わりではありません。ただ空気を調整するだけではダメなのです・・・ここで問題になるのは、低圧で走るとパンクのリスクがある という点です。最初に紹介したように、オフロードバイクはチューブホイールが基本なので、チューブを損傷するとパンク=走行不能となってしまいます。何故低圧で走るとパンクのリスクがあるのか?理由は二つあります。一つはバルブのズレによるバルブもげという現象。もう一つはリム打ちパンクという現象です。順番に解説しましょう。バルブもげまず、バルブもげというのは、言葉の通りチューブのバルブ部分がもげて(千切れて)しまう現象です。何故こんなことが起こるのか?それは空気を抜いて低圧で走ると、タイヤ・チューブ・リムの3点の維持力が弱くなります。内圧が低いので押さえつける力も弱くなりますしね。そうなると、エンジンの力やブレーキの力に負けてタイヤがズレてしまう(空回りしてしまう)ことがあります。このとき、チューブのバルブがナットでしっかり固定されていると、力の逃げ場がなく根元からバルブがもげてしまうことに。バルブがもげると当然空気は全て抜けてしまい、パンクとなります。釘を踏んだパンクと異なり、パッチを貼っての修理は出来ません。チューブ交換が必須となりますが林道でチューブを携行しているとは限りません。バルブもげというのは恐ろしいトラブルです・・・。これがバルブもげの原因です。対策としては、バルブナットを締めない・もしくは付けないということが第一。そしてビードストッパーを装着することです。ビードストッパーとはビードストッパーというのは、言葉の通り「ビードを止める」というパーツ。メーカーによってはリムロックと名付けていますが、「リムを固定する」という意味で、どちらも同じことを視点を変えて名付けているだけの同一パーツです。目的はタイヤのリムと接触している部分であるビードがリムとズレないように、内部から押さえつけるというもの。ビードをストップさせる、もしくはリムをロックする、同じことですね。シンプルな構造ですが、バルブもげにはとても有効な対策で空気圧を1.0kpa以下にする場合には装着必須と言って良いでしょう。前後輪に1個ずつ装着するのが基本ですが、エンジンの力を直接受ける後輪には2つ以上装着することも。空気圧が0.6kpaを下回る辺りから2個装着しておくと良いかと思います。[card_p : product_id=668]ビードストッパーには重いが壊れない金属製(DUNLOP・DRC)と、軽いがたまに壊れるプラスチック製(MOTION-PRO)があります。[card_p : product_id=35466]金属製も使用に伴いゴムと金属と剥離が起こるので定期交換は必要ですが、一長一短なのでここはお好みでお選びください。リム打ちパンクリム打ちパンクというのは尖った石などの障害物・固い路面への激しい着地など大きくタイヤが変形する際に、リムとタイヤ(越しの障害物)にチューブが挟まれることで穴が開いてしまう現象です。これも低圧にすればするほど発生率の上がるトラブルですが、この対策というのはとてもシンプル。チューブの厚みを増やせば良いと言うことです。そこで登場するのがハードチューブ。ハードチューブとは通常のノーマルチューブの倍程度の厚みを持たせたチューブで、物理的に穴が開きにくくなっています。実に単純明快です。そして更に対パンク性能を向上させて、スーパーヘビーチューブというものもあります。[card_p : product_id=834]スーパーヘビーチューブとはこれはハードチューブが更に倍の厚みになったもので、梱包状態で並べてみるとこの通り。重さもしっかり増加していて、走りへのデメリットも無視できないレベルです。バネした重量の軽量化は効果が~なんて良く言いますが、それに完全に逆行する暴挙です。オフロードを楽しく走ろうと思うと、パンクしてはどうしようもないのでハードチューブは基本装備と言って良いでしょう。モトクロッサーなども標準で装着しています。スーパーヘビーチューブまで使用するかどうか?ここは走りの質とトラブル回避を天秤に掛けて検討する必要があります。難しいところですね。[card_p : product_id=832]今回は空気圧の話から逸脱するので除外しますが、パンク対策の究極形としてチューブの代わりに発泡体を詰め込むタイヤムースというものもあります。 まとめそんな訳で、空気圧を低圧にした場合の問題と対処はこのようなお話となっております。これらの対策さえしっかりと行っていれば、自身の思う空気圧設定でリスクを押さえて楽しく乗れると思います。人によって考え方が多様なテーマなので、実際に調整を試してトライ&エラーで丁度良い設定を見つけてくださいね。当店ことダートバイクプラスでは、タイヤの選び方はもちろんチューブやビードストッパーとの組み合わせや取り付け作業など、タイヤ全般幅広くサポートしております。不明な点などございましたら遠慮なくお問い合わせください。オフロードバイク用品買うなら!ダートバイクプラスを是非どうぞ!
もっと読む